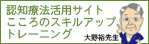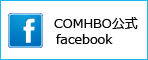コンボの動き
vol.144 コンボが主催・開催した活動や今後の開催予定です。
○「こころの元気+」2025年10月号より
○申込について ○申込はこちら
○224号へ戻る
○2025年8月2日開催 ※今後のこんぼ亭は→コチラ
第99回こんぼ亭 ※終了したこんぼ亭は→コチラ
「声や妄想にふりまわされない暮らし方
ヒアリング・ヴォイシズによる対処と理解の探求」 報告
コンボ事務局より
▼参考:2025年1月号の「こころの元気+」より
●ヒアリング・ヴォイシズって何ですか? →こちら
2025年8月2日㈯に第99回こんぼ亭「声や妄想にふりまわされない暮らし方~ヒアリング・ヴォイシズによる対処と理解の探求~」をオンラインで開催しました。
前半は、佐藤和喜雄さん(ヒアリング・ヴォイシズ研究会/NPO法人福祉会菩提樹)にヒアリング・ヴォイシズについて話していただきました(▼写真)。
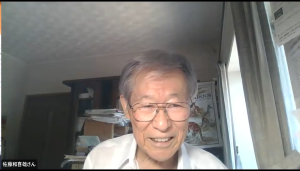
「幻聴」ではなく「聴声(声が聴こえる)」と呼んでいること、6%の人(2千人中)が声を聴いたことがあると回答した調査結果など、興味深い内容でした。
後半は、ライブで参加者の以下のような質問に答えていただきました。
▼Q&Aより(10月号に掲載した以外の質問もご紹介)
●声を肯定的にとらえれば、声とうまくつきあえるとのことですが、どうすれば声を肯定的にとらえられますか?
●幻聴の怖い気持ちや声の内容について話せる人がいることが大切というお話がありました。私の妻も幻聴が聞こえることがあり、その内奥についてなるべく否定せず聴くようにしています。しかし、幻聴の内容を聞いている自分自身がとても疲労してしまいます。そのようなときはどうしたらよいのでしょうか?
●話に出てきたマーストリヒト面接法(または、この活動)は、どこで受けられますか?
●家族です。大変興味深く、オープンダイアローグのケアと重ねて聞かせていただきました。
本人は統合失調症と診断されています。
ヒアリングヴォイシズの自覚がなく、生活に混乱をきたしています。
向き合えるよう働きかけをした方がいいのでしょうか。また、どのようにできますか?
●強迫性障害やくり返しのイヤな思いなどにも対応できますか?
▼開催後アンケート(一部抜粋)
開催後に参加者からいただいたアンケートを(10月号に掲載した以外のものも)いくつかご紹介します。
●私も10代で今で思えば「幻聴」と「幻覚」に悩まされていました。
親に相談しましたが、「そんなはずない」と否定されそれ以来誰にも話さずにきましたが、多分「幻聴」だったのだろうと今では思います。
もっと「声が聞こえる」ことがあるのだということが特に思春期の多感な時期に知ることができる社会になれば私の今も続く苦しみは軽減できたのかなあと思います。
ですから、世界中で「声が聞こえる」人がいるという今回のコンボ亭は本当に「心からほっとできる」時間になりました。自分だけではなかった、ということが孤独で孤立していて誰にもわかってもらえない当事者にどれほどの安堵を与えることか。これは当事者でないとわからないかもしれません。 (当事者・匿名)
●タイトルからは幻聴に対処するスキルなのかと思いましたが、そうではなくて、パートナーシップや見える化が重要とわかり、生活に密着しているのがいいなと思いました。 (専門職・匿名)
●症状ありき、また、さらに進んで、その人らしさその人の努力を意識した質問の仕方が重要だと分かった点がとても良かったです。 (当事者Aさん)
●当事者(息子)が語る幻聴を、どう聞けばプラス(何らかの回復の方向)に持っていけるのか、いつも探っています。
今日の具体例に試してみようと思うヒントがたくさんありました。
息子の幻聴について聞くことが負担というのは私も感じるところですが、「耳をふさがずちゃんと聞こう」と元気が出てくるお話でした。 (親・匿名)
●本格的に取り組むには、面接法を学ばなければならないですが、「パートナーシップ」「見える化」「ありのままを受け止める」「その方自身がすでにしている対処法を教えてもらう」等々、日常的に大切にしていることと重なり、活かせることがたくさんありました。 (専門職・匿名)
●かなり身近なテーマで高い関心がありました。
それにしても、こんな身近過ぎるテーマに、医療分野が追いついていないことに驚きました。
もっと広く周知する方法はないものでしょうか? (りっちゃん)
●ヒアリング・ヴォイシズは当事者の立場に立ってくれている考え方だなと感じました。 (まめたさん)
○「こころの元気+」2025年10月号より
○申込について ○申込はこちら
○224号へ戻る