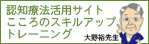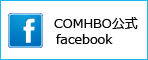特集2
「始められない」にも理由がある(224号)
○「こころの元気+」2025年10月号より
○申込について ○申込はこちら
○224号へ戻る
筆者:江藤愛子
千葉大学 子どものこころの発達教育研究センター
特任研究員
▼こんな経験
「今日こそやろう」と思っても体が動かない。
目覚ましが鳴っても布団から出られない。
やろうと決めたのに、どうしても始められない。
怠けているから、意志が弱いからと自分を責めてしまった経験はありませんか?
実はその背景には、誰にでも起こりうる心や体の状態による要因があります。
今回は「始められない」理由と、その対策について考えてみたいと思います。
▼「始められない」背景にある要因
私達が行動を起こすとき、頭の中ではさまざまな思考や感情が動いています。
その中で、次のような要因が最初の一歩を踏み出すのをむずかしくしているかもしれません。
①予期不安
「やってもうまくいかないのでは」
「失敗したらどうしよう」
と未来を悲観的に予想してしまう状態です。
行動の先にある失敗のイメージが強くなるほど、挑戦は怖いものになり、避けたくなります。
②完璧主義と失敗への恐れ
「完璧にできなければ意味がない」
と思うと、行動のハードルがぐっと高くなります。
そのプレッシャーから気持ちが重くなり、
「どうせうまくできないなら始めないほうがいい」
と感じてしまうことがあります。
③ネガティブな感情による錯覚
やらなければいけない課題に取りかかる前に、
「面倒くさそう」と感じることがあります。
すると、実際より課題が大きくて複雑でむずかしいもののように思えてしまいます。
その結果、手をつけられず、先延ばしになることがあります。
④エネルギーの低下
疲労やストレス、うつ症状などがあると、行動するための心理的エネルギーそのものが不足します。
この場合、始められないのは心身が休息を必要としているサインでもあります。
①~④などの要因が重なって、始められないという状態が起こることがあります。
▼認知行動療法の視点からできること
認知行動療法(CBT)は、自分の考え方や行動のパターンに気づき、少しずつ考え方や行動を工夫していく心理療法です。
「始められない」と感じるときも、自分の思考のくせに気づき、少し違う考え方や行動を試すことで心が軽くなり、動きやすくなることがあります。
◎頭に浮かぶことに注目
まず、始められないときに、頭に浮かんだことに注目してみましょう。
「失敗したらどうしよう」と未来を悲観しすぎていないか、
「完璧にできなければ意味がない」と思いこんでいないかを確認してみましょう。
「失敗しても学びがある」
「小さく試すだけでもいい」
と考えてみることで、一歩を踏み出しやすくなるかもしれません。
◎小さく分ける
また、大変そうに思える課題をできるだけ小さく分解するのも効果的です。
たとえば「部屋を片づける」ではなく、「机の上の紙を1枚だけ捨てる」と設定します。
行動のハードルを極端に下げることで、心理的な負担が減り、先延ばししにくくなります。
◎責めない
さらに、始められない自分を責めないことも大切です。
自分を責めると前向きな気持ちが削がれ、気分が落ちこみ、ますます行動しづらくなってしまうことがあります。
▼始められない自分は、何かを始めたい自分
行動を始められないのは、怠けや意志が弱いからではありません。
始められない背景にはさまざまな理由があるのです。
「始められない」と悩むのは、「何かを始めたい、変えたい」と思っているサインでもあります。
そのような前向きな気持ちを持っている自分をまず認めて、ほめてあげることから始めてみませんか。
そして、その後、「始められないのはどんな理由があるのかな?」と自分を観察して、今の自分にできそうなほんの小さな工夫を探してみるとよいかもしれません。