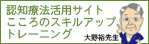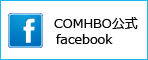コンボの動き
vol.145 コンボが主催・開催した活動や今後の開催予定です。
○「こころの元気+」2025年11月号より
○申込について ○申込はこちら
○225号へ戻る
○2025年9月20日開催 ※今後のこんぼ亭は→コチラ
第100回こんぼ亭 ※終了したこんぼ亭は→コチラ
「診断名でなく私を見て。
精神科医療の新しい扉を開く」 報告
コンボ事務局より
2025年9月20日㈯、第100回目のこんぼ亭「診断名でなく私を見て。精神科医療の新しい扉を開く」をオンラインで開催しました。
▼前半は対談中心、後半はQ&A
今回はいつもと趣向を変えて、最初に伊藤順一郎さん(コンボ共同代表・しっぽふぁーれ)、次に遊佐安一郎さん(長谷川メンタルヘルス研究所・コンボ監事)のそれぞれに「診断名」についての自分の考え方の変化や歴史を話してもらいました。
その後はお二人で、今回のテーマをめぐって、医療の現場とカウンセリングの現場で体験したこと・感じたことなどを含めた対談を繰り広げてもらいました。
後半のトークライブでは、前半の対談を聞いた皆さんからの質問に、亭主(案内役)市来真彦さんをまじえて、リアルタイムで答えてもらいました。
▼Q&Aより(11月号に掲載した以外の質問もご紹介)
○怖い声が聞こえ、症状がなかなか改善せずつらい思いをしています。
オープンダイアローグやPTMF(※)をうけることで 少しでもよくなればと切に願っていますが、どこでうけられるのかお教えください。
(※PTMF(Power Threat Meaning Framework) :精神的困難や「こころの問題」を理解するための新しい枠組み)
○患者の背景を探るのは病院だけではむずかしく、患者を知るために横のつながり(家族や友人、職場?)や患者を取り巻く環境とのつながりが必要になると思います。
どうお考えですか?
○「回復・治る」とは? また、逆に言うと治療とは?
私的には「自分を客観的に見られる」これが「治った・回復」と言いたいのですが何か足りない…。
○心療内科をしている医師です。多くの精神疾患はトラウマがもとにあるのでは?
○ハラスメントとトラウマの関係は?
○家族です。病名告知のタイミングはいつがいいですか?
遅いと、病識が持てずに薬をのまない、通院しないなどが起こるのでは?
▼開催後アンケートより
開催後に参加者からいただいたアンケートを(11月号に掲載した以外のものも含め)いくつかご紹介します。
●こんぼ亭記念すべき100回とのこと、おめでとうございます。
今回のテーマである『診断名』ではなく『私』を見て。という言葉にひかれました。
診断名に重きをおいてしまうのは、私たち当事者でもあるあるで、一定のイメージをもってしまいがちです。
自分の病気(統合失調症)以外の病気に関しては、私も想像するしかないので、当事者であっても、その人をみる視点をもつことは、ピアサポート等仲間作りではとても大事な視点になってくると思います。
診断名が壁になって、わかろうとする努力を奪うのはあってはいけないと思います。
精神科医療の中で、人をみるという視点が変化につながっているんだな、と感じました。
それはとても意義深いことながら、人はそれぞれ違うので、大変であると思います。
でも、それにチャレンジしてくださっている方々がいることに当事者としては喜びを感じますし、自分たちの存在が尊重されることはありがたいと思いました。
(ていさん)
●今回の企画、とてもよかったです。
多くの方に視聴していただきたいと思いました。
伊藤さん遊佐さんのお人柄が画面を通して感じられました。
常々医療・専門職の方には「私の話をしっかり聴いて、ちゃんと憶えていてください」と感じて来ました。
あしらわれたり約束を反故にされたり、何度も話したり文章にしていても記憶されていないことが多く、傷付き落胆しています。
ご多忙だし、たくさんの人と関わっているから仕方ないのだと思おうとしてはいますが‥。
地元ではない田舎暮らし、家族も友人もなく、ほとんど引きこもりの私にとって、主治医や専門職の方がわずかな人とのつながりでもあるのです。
逆に私も皆さんの人生をじっくり伺いたい気持ちが強くあります。
(エイチさん)
●遊佐先生と伊藤先生のお話を聞きながら泣いてしまいました。
ここ数日の交錯する過去と現在のトラウマのフラッシュバックで急速に活力が落ち、泣ければ楽なのに泣きたい想いだけが続く、胸がふさがる鬱状態でした。
少し泣けてまた歩めます。
今回「おうちでこんぼ100回記念」に大きな癒しのプレゼントをいただきました。
ファシリテーター含め先生方に心から感謝いたします。
(まーまゆさん)
●少し前に、精神科領域の訪問看護のお仕事につき始めました。
はじめは、自分がどういうお役目をしていけばよいのかまったく分からず、病名の書かれた本を眺めてはやれることの答え探しをしていました。でも、どうにも当てはまらず、どうしてよいかわからぬまま訪問に通い続けました。
その方のリアルに触れるうちに、メンタルサポートというのは病名ではなく、その方自身の今と、人生物語に視点を向けて、そのつどのご本人の困りごとの対処法を共に考えていくことなのかな?
どうしていきたくて、何ならやれそうなのか、答えもペースもその方にしかなく、時間をかけてゆっくり、行きつ戻りつの揺らぎも見守りながら伴走していくことなのかな? と最近になり感じ始めたところでした。
そのため今回のテーマは腑に落ちる内容ばかりで、考え方や学んでみたい情報(オープンダイアローグ、家族療法など)は大変参考になり、始まったばかりのメンタルヘルスに関わるお仕事にやりがいを感じ大変うれしい気持ちになりました。
伊藤先生の丁寧でゆったりとした口調と分かりやすい言葉選びが、とてもよかったです。
地域の精神科の先生が伊藤先生のような感性で力になってくれたらどんなに心強く有意義だろうかと切に感じました。、
遊佐先生のクライアントさんとのいくつかのエピソードが興味深く、もっと詳しく聞きたいなあと思いました。
(ふくねこさん)
●医療者側の意見や考え方が、患者側からではわからない点が以前からあったが、今回の話で少しずつ理解できるようになりました。
(当事者Aさん)
●伊藤先生の「病気を治すことが目的ではなく、生きることに寄り添うのが大切」という言葉がとてもうれしかったです。
現実には、生きる場は医療機関以外にも、さまざまな人と場所にかかわるので、そうした福祉現場の方々にこうした考え方を浸透できたらいいなと思いました。
(市川の家族さん)
●環境の中で困りごとが起こり、どうしたらその困りごとを解消できるのか、診断名は保険診療で必要なことであるが、大事なことはその人の困りごとをどうしたらよいか一緒に考えること、その言葉が印象的でした。
ありがとうございました。
(匿名希望)