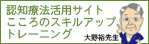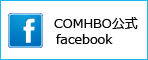→「こころの元気+」 →「こころの元気+」(賛助会員)の申込方法
「こころの元気+」連載
性をタブーにしない
▼目次
○内容
○各回のタイトル
○執筆者
○その他
「性」は最もタブーなテーマの1つでしょう。
「性」と聞くと、性交渉を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、「性」を幅広く捉えると、性役割・家族のあり方・親密な関係・性的マイノリティ・子どもを産むか産まないかなど幅広いことが含まれます。
この連載では、研究チームの当事者・専門職のメンバーが、「性」を幅広い側面からお伝えします。読者の皆様が「性をタブーにしない」と思えるようになる連載をめざします。(第1回の連載より)
▼くわしくは
※精神疾患のある人の性と生殖に関する健康と権利のホームページ
○目次に戻る
▼各回のタイトル
▼2026年
1月号(227号)9回 生理の大切さ/まる(横浜ピアスタッフ協会)日下桃子(湘南医療大学)
▼2025年
12月号(226号)8回 病院医療や看護からみたセクシュアリティ/横山惠子(横浜創英大学看護学部)
11月号(225号)7回 ポルノと性感染症について考えること/野間慎太郎(ピアサポートグループ「ハマッチャ」)
10月号(224号)6回 「好き」はタブーではない ~LGBTQ+の生きざまから/ソウ(あいりきファシリテーター)
9月号(223号)5回 専門職が性についての相談を受けたときに考えること/白石泰三(Q-ACT)
8月号(222号)4回 快楽・セルフプレジャー/ねもやん(「あいりき」ファシリテーター)
7月号(221号)3回 性教育を「支援」の視点から考える/高橋幸子(医療人育成支援センター・地域医学推進センター)
6月号(220号)2回 精神疾患と性:歴史と研究/蔭山正子(大阪大学高等共創研究院)
5月号(219号)1回「性をタブーにしない」でお伝えすること/蔭山正子(大阪大学高等共創研究院)←初回のため全文公開
▼連載の執筆者
▼蔭山正子(大阪大学高等共創研究院)
大学教員で、職種は保健師です。
研究テーマは家族支援を中心に、育児・恋愛・性と生殖などでいつも当事者や家族の方と一緒に取り組んでいます。
この連載では、精神疾患と性についての歴史や研究をお伝えします。
▼市橋香代(東京大学医学部附属病院 精神神経科)
大学病院の精神科医で、医学生の臨床実習担当もしています。
精神障がい者の恋愛・結婚に関するプログラム「あいりき」の他に「うけコツ」という統合失調症薬物治療ガイドを広める活動をしています。
「診察室で性について話すこと」について取り上げます。
▼まる(横浜ピアスタッフ協会)
B型作業所でピアスタッフとして働きながら、障害のある人が演劇をする「アウトバック」で演劇をしたり、「あいりき」でピア活動をしています。
生理中の性行為と生理の大切さについて、自身の体験をもとに話したいと思います。
▼日下桃子(湘南医療大学保険医療学部 看護学科)
私は看護教員として働く助産師です。
家族がうつ病になったことがきっかけで看護職を志しました。
「精神疾患のある女性と家族が妊娠、出産、子育てをする上で起きるかもしれないこと」についてお伝えします。
▼高橋幸子(埼玉医科大学)
埼玉で産婦人科医をしています。専門は「包括的性教育」です。
ジェンダー平等や人権をベースにしたポジティブな性教育についてお伝えします。
▼ソウ
自分のペースで仕事をしながら、「あいりき」などでピアサポーターとして活動しています。
私は、性の多様性・性的マイノリティと精神疾患の関連性などのお話を、私自身の体験をもとにお話しさせていただきます。
▼ねもやん
横浜を中心に「あいりき」「めんちゃれ」、電話相談、ピアカウンセリング、「引きこもりSOS」「瀬谷ゆるり会」「いずみ会」などを開催・担当・参加等しています。
この連載では、快楽、セルフプレジャーについて担当します。
▼横山惠子(横浜創英大学看護学部 精神看護学)
大学の教員で、職種は看護師です。
家族支援を研究テーマとして、当事者と家族が元気になる活動をしています。
これまでの経験から、家族や医療者が「性」をタブーとしている現状、今後必要とされる姿をお伝えします。
▼白石泰三(Q-ACT)
職種は、精神保健福祉士です。
精神科に通院中の方への訪問での生活支援や入院中の方の退院支援を行っています。
「支援者が性の相談を受けたときに考えること」についてお伝えします。
▼野間慎太郎(オンラインフリースペース「ハマッチャ」共同代表「あいりき」ファシリテーター)
中間支援組織で働きつつ、仲間と「ハマッチャ」の運営や「あいりき」に携わるピアサポーターです。
自身の経験をもとに、性感染症やポルノとの向き合い方についてお伝えします。
○目次に戻る
▼その他
連載内に掲載されている調査や研究などについては下記をご覧ください。
※精神疾患のある人の性と生殖に関する健康と権利のホームページ