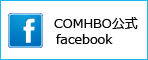「こころの元気+」2015年2月号(96号)より→『こころの元気+』とは
(バックナンバーからの転載ですので掲載時の情報であることにご注意下さい)
○「こころの元気+」の申込について
特集3 精神科医はどうやって診断しているのか
久留米大学医学部 神経精神医学講座
内野俊郎
腹痛で内科を受診すると、いつから痛いかといった問診やお腹を触って調べる触診が行われます。
血液検査も多いでしょう。
それらに加えてレントゲンやエコー、場合によってはCTといった検査で診断を行うこともあります。また、糖尿病など血液検査である程度の診断がはっきりする病気もあります。
ところが、統合失調症やうつ病、双極性障がいといった精神科の病気は、そういった客観的なデータや画像だけで診断するのはまだ不可能です。
脳波検査やCT検査を行うことはありますが、これは他の病気との区別をつけるために行われるもの(鑑別診断)です。そのため、精神科の病気の診断に最も重視される方法は、患者さんの体験を言葉で語ってもらうことによる問診ということになります。
これはより専門的に行われることから精神科的診断面接と呼ばれることもあり、ご本人だけではなく、様子をよく知る近親者の話を伺って判断することもあります。
また、1回の面接だけで診断がつかないこともありますし、患者さんの状態によりますが、ある程度の治療の方針を立て必要な診断をつけるためには1時間程度は必要になることが多いように思います。
その1時間で、困っていること(症状)は具体的にどのようなものか、その症状はいつ頃からか、どんな対処をしてきたのかといったことや、症状が起きる前にどのような生活の背景があり、他に体や気持ちの変調はないかという情報を集めていきます。
ただ、とても多くの患者さんが受診している状況でその1時間をどう確保するかというのは、精神科医にとっても患者さんにとっても切実な課題といえるでしょう。
○診断が大切なわけ
望ましい治療のために確実な診断が第一歩になることはいうまでもありません。
診断が異なれば、治療法が変わってしまうわけですから当然のことです。特に最近では、うつ病と双極性障がい(旧 躁うつ病)をできるだけ早期に区別することが注目されています。
どちらも同じように抑うつ状態を経験するのですが、長期的に見たときには選ぶべき薬がかなり違うことがわかってきたからです。
また、統合失調症でも最初に抑うつ状態で発症する方がいますが、当然薬の選択は異なります。
しかし、現実にはそれらの区別はなかなか容易ではありません。
皆さんには、NIRSという装置を用いた診断の方法を耳にした方もあるかもしれません。
これは頭の表面から近赤外線という光をあて、反射する光を測定することで客観的に脳の働きを検査するというもの(光トポグラフィー検査)で、うつ病や双極性障がい、統合失調症の区別ができるという研究報告もあります。
しかし現在は先進的な医療技術の段階とされており、広く実施されるようになるにはもう少し研究成果を積み上げる必要がありそうです。
より望ましい治療を早く患者さんに提供するために、診断方法はこれからも進歩していくことが期待されます。
○診断が変わるのは誤診なのか?
最初の病院と2つ目の病院で診断が違っていたという話は精神科に限らずよく耳にします。
そういった場合、最初の診断は誤診だったのでしょうか?
実際に診療をしている立場からすると、誤診といえる場合と誤診とはいえない場合があるように思います。
他の病気の可能性も考えるのが当然な症状があるのにそれを見逃している場合や、よく似た症状を起こす別の病気でも、頻度の多いものや、ちょっとした質問や検査の追加で区別できるのに、それをしないことで起こったものは誤診といえるように思います。
一方、後から診断が変わったのに誤診といえないケースとはどういうものでしょう。
私が経験したある方のお話を少しだけ紹介します。
大学を卒業したばかりの女性Aさんは「眠れない」という訴えで受診しました。
寝つきが悪く、朝もすっきりしないというお話をされました。
悲しい気分や仕事への不安などはなく、昼間眠気を感じても仕事にもきちんと取り組めているとおっしゃいます。
念のために甲状腺の検査などもしましたが異常はありません。
また、誰もいないのに声が聴こえるという体験などは一度もないと笑顔で返されました。
やはり1時間程度の診察でいろいろな病気の可能性を考えてみましたが、不眠の他には時々経験する動悸が気になるということしかはっきりしませんでした。
その段階ではいわゆる「不眠症」としか考えられず、質のよい眠りに役立つ生活の工夫を話して数回分の睡眠導入剤を出しました。
しかしその数か月後には、Aさんの行動を非難する幻聴や外出先で監視されているといった体験がはっきりと出てくるようになりました。
Aさんがまず経験した不眠は、統合失調症が発症する前の最初の変化として起こってきたものと考えられました。
さらにAさんには、1年ほどしてから急激に気分が高揚して過剰に活動的となる状態や幻聴や妄想の悪化とは別に、気分が急激に沈みこむといった気分の浮き沈みもみられるようになり、「統合失調感情障がい」という病気の特徴が次第にはっきりするようになっていきました。
その間、Aさんの診断は、「不眠症」から「統合失調症」、さらに「統合失調感情障がい」という形で変化していったことになります。
診断した私がこう書くのもどうかとは思いますが、こういったケースを誤診と考えるのはややむずかしいように思います。
特に初診の段階でその後の幻覚妄想や気分の変動を予測することは、今の知識や経験を総動員しても無理ではないかと考えるのです。
○後医は良医
後から診たお医者さんの診断が正しかった、それはそのお医者さんの腕がよりよかったからだという話をしばしば耳にします。
しかし、後から診る医師はそれまでの経過を踏まえて判断できるので、医師の力量が同じでも、より正確な診断に近づきやすいわけです。
最初の診断にもとづいて治療を行い、その反応で別の病気を考えるという過程は正確な診断にはとても大切なことですので、別の医師の意見を聞きたいときは、それまでの医師がどのように考え、どんな治療をしたかがはっきりするような紹介状を書いてもらうことを強くお勧めします。
○正しい診断が出にくいのは?
これにはさまざまな要因が影響しますが、発症から間もないケースというのは代表的なものかもしれません。
Aさんもそうでしたが、初期には医師が診断の根拠とする症状が揃っていない場合も珍しくありません。
一時期しか起こらない症状もあり、再び起こるまでは診断が明らかにならない場合もあります。
また、うつ状態で始まる病気はかなり幅が広く、
最終的にも「うつ病」である方、
その後躁状態があり「双極性障がい」と診断される方、
「統合失調症」の始まりがうつ状態である方などは、診断が途中から変わる可能性が高いかもしれません。
また、うつ状態が「認知症」の始まりであることはよく知られた事実です。
※うつ病についての書籍 →当事者・家族のための わかりやすいうつ病治療ガイド
医師が把握できる情報に偏りがあることも診断がきちんと行えない要因になります。
患者さんの困っている症状を医師がきちんと聞かないのは問題外ですが、診断に必要な症状と当事者が困っている症状が必ずしも同じとは限らないのです。
特に軽い躁状態は、当事者があまり困っていないどころか、むしろ「調子がよい」と認識されがちで、ご本人からはあまり語られることがありません。
そのため、躁状態の存在に医師が気づかないままに時間が経つことは珍しくないように思います。
※双極性障害(躁うつ病)についての書籍 →双極性障害Q&A 人生行ったり来たりがリカバリー!
また、「こんなことを言うと病気だと思われるから…」という不安から、数年前から幻聴があったことを口にできなかった患者さんもいました。
自分の体験を医師にすべて伝えるのはむずかしいことですが、家族や支援者の協力を得ながら診断に役立つ情報を医師に伝えるのは、正しい診断への近道といえるでしょう。
○診断が心配になったら
苦しいのがなかなか楽にならない、自分と似た症状のBさんは違う病名らしい、今の薬を調べたら自分とは違う病気の治療薬のようだ…など、「ひょっとしたら自分は違う病気なのではないか」と心配になることがあるかもしれません。
少しでも正確な診断のもとで症状が改善すればと思うのは自然なことです。
そんなとき別の医師の意見を聞いてみる、いわゆるセカンドオピニオンを受けるのは一つの解決の手段です。
その場合には、先にも述べたように今の主治医に紹介状を書いてもらってください。
なかなか頼みづらいという方もいますが、自分で把握している症状以外にも診断に役立つ情報を医師がきちんと伝えることは、セカンドオピニオンの医師の判断にとても重要なことがあります。
前の医師からの情報がないと、何人の医師に診てもらっても同じ診断のくり返しになってしまうことにもなりかねません。
勇気が必要と感じる方もいるでしょうが、ぜひ主治医に求められることをお勧めします。
また、誤診ではないかと心配になったとき、今の主治医にその気持ちを伝えることが解決への一番の早道のようにも思います。
いろいろな尋ね方があるでしょうが、
私ならば「誤診じゃないですか?」とは聞かずに
「ひょっとしたら別の病気もあるんじゃないかと心配しています」
といった言い回しを選びます。
なぜそういう心配が生まれたかを伝えれば、多くの医師は今の診断になった理由を説明してくれるでしょう。
そのコミュニケーションがうまくいかない場合や説明に納得しなかった場合にセカンドオピニオンという選択を考えてもよいかもしれません。
血液検査やCT等、客観的な方法だけで診断がまだ困難な精神科の病気が多い現状、患者さんの体験を医師が耳で聞き、場合によっては目でも見て把握することが大きな柱となります。
調子の悪いときは体験を説明するのも容易ではないことでしょう。
診断するのは医師の仕事であり、医師がそのための力量を高めるべく精進し続けなければならないのは当然ですが、患者さんと一緒に診断を考えていくのもまた大切なことなのです。
▲「こころの元気+」2015年2月号(96号)より
→『こころの元気+』とは