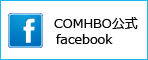こころの元気+ 2012年3月号特集より
特集2
精神科での漢方の広がり
神経科浜松病院
井口博登
漢方薬について
薬局に行くと、最先端の技術を使ったパブロン、コンタックなどの風邪薬と一緒に、葛根湯や小青竜湯、柴胡桂枝湯などといった漢方薬が負けずに並んでいて、内服したことのある方も少なくないと思います。
これらの処方は、いずれも、約一八〇〇年前に中国で編纂された、今でいうとインフルエンザのような重症化する風邪の治療法を書いた「傷寒論」という書物に載っているものなのです。
そういった処方が、今でも現役で、それも身近に、風邪薬として利用されていることからも、漢方薬に秘められている知恵の奥深さが感じられます。
西洋医学が明治以降に本格的に日本に入ってくる前までは、日本の医療は、おもに漢方医学によって支えられていました。
では、精神科はどうしていたのかというと、漢方医学では、精神の症状と、体の症状を分けて考えることはしておらず、体の構成要素や機能のバランスの失調に伴っていろいろな精神の症状も出てくると考えていました。
ですから、昔の漢方の本には、発熱や尿の出方、便秘、下痢、動悸、呼吸が浅い、汗が出る、などの体の症状と一緒に、落ち着かない、うつうつとしている、驚きやすい、眠れない、うわごとを言う、などといった精神症状が書かれています。それらの心身の症状の組み合わせに対して、どのような処方や対応が効果的なのかといったことが論じられています。
また、心身の症状の他にも、脈の緊張をみる、舌の色や苔(付着物)をみる、腹部の緊張や圧痛をみるといった漢方独特の診察方法があって、それらを合わせて処方を選んでいくといったことをしていました。
精神科での漢方薬の使われ方
現在の精神科での医療は、体の症状は、内科や他の身体科で扱い、精神の症状をもっぱら取り上げて、それに対して診断、治療をしていくといったものとなっています。
逆にそうすることによって、神経や脳の働きと、精神の症状との関連の研究が進み、漢方薬では得られないような効果を示す、精神科のさまざまな薬が発達してきました。統合失調症や、躁うつ病、うつ病、てんかんなどの典型的な症状に対して、漢方薬は、今の精神科の薬にはとても及ばないところがあります。
しかし最近になって、漢方薬が比較的よく精神科でも使われるようになりました。特に、高齢者の認知症でみられる、軽い幻覚や妄想、興奮、怒りっぽいといった症状に対して、抑肝散という薬の効果がしっかりした研究で認められました。
さらに、錠剤の鎮静薬でみられる、ふらつきや転倒、むせこみといった副作用もないことから、昔の漢方の理論によらずに、西洋医学の診断に沿って、多く利用されるようになっています。
それ以外にも、口の渇き、手のふるえ、便秘、吐き気といった精神科の薬の副作用に、対症療法的に、さまざまな漢方薬が利用されることもあり、また、軽症のうつ病や境界性パーソナリティ障害に利用して効果があったという研究もみられるようになってきました。
もちろん、現在でも、比較的精神の症状が軽く、特徴的な身体症状がみられる場合は、昔ながらの身体症状と精神症状を合わせて、さらに、身体診察をしたうえで、個別に患者にあった処方をしていくといった漢方治療もなされています。
西洋医学を補うように、漢方薬を有効利用することで、精神科での薬物治療の幅が広がってくると考えられています。