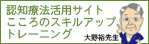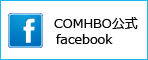こころの元気+ 2010年3月号特集より
特集5
役に立ちたいと思っている人への接し方
Office夢風舎・フリーランスナース&ソーシャルワーカー
土屋徹
皆さんは、自己肯定感という言葉には、どのような意味があると思いますか?
いろいろ調べてみると、
「健全な自我を持っていて、自分自身を愛し、自分を認めることができる」という感覚であるとか、
「自分のことが好きである」という感情と書いてあります。
また、初めは「自分のよいところだけ好き」という感覚から、「自分のよいところや悪いところも含めて好きになる」という、「ありのままの自己」を受けとめることができることだそうです。
自己肯定感は、欧米と日本の中学生を比べた報告では、日本人の方が低いという報告もあります。精神科の病気になったから、自己肯定感が下がってしまうという感じもしますが、病気や障害に関係なく小さい頃から低い人も多くいるのです。
私も、「自分はこの仕事に対して本当に役に立っているのか?」と思ったことなどもたくさんあります。
まわりの人に合わせようと
自己肯定感の低い人たちは、まわりの人たちに合わせようと努力しています。
自分自身を認めてもらいたくて、自分の力以上の自分を表現したり、背伸びをしたりしていることがあります。
ですから、まわりの人からは「何をそんなに無理をしているのかな」、「できないことを無理にやっている」というようにとらえられてしまうこともあるのです。
自己肯定感が低いと思われるようなことは誰にでもあり、そのように思うことや表現することは、決して特別なことではないのだと思います。
今の自分でいい
ちょっとしたやりとりを書いてみます。
「お父さん、僕は毎日仕事で役に立っていない。仕事に行ってもダメな人間だと思うんだ」
と言われて、
①「そうなんだ、自分をダメな人間だと思うんだね。何でダメな人間だと思うのかな?」
②「毎日仕事に行っているということは、がんばってるんだよね。みんなからどのように見てほしいのかな?」
③「そうか、仕事に行っているときに、そんなふうに思ってしまうんだ。これから先はもっとどんなふうになっていきたいの?」
それぞれのやりとりには特徴があります。どれがいいとか悪いとかではなく、いろいろなやりとりが行われるでしょう。
①は、「なぜなぜモード」の原因追及モデルの質問です。
そもそも自分のことを低くとらえている人たちに、もっともっとダメな自分を、自分の口から出させてしまうことになります。
②は、「みんなからがんばってるって言ってほしいんだよ」と自分の口から言わせるような質問です。自分からこのような言葉がほしいというのは、少し恥ずかしいかもしれません。
③は、「自分自身のがんばり探しをする」、「これから先の前向きな自分をつくっていく」質問の仕方です。
自己肯定感の低い人への関わりは、
「これから先のことを語り合う。今できていることに注目する」などが大切です。
そのようなやりとりが増えたり何度も繰り返すことで、自分自身を前向きに肯定的にとらえることができていくのです。
これにプラスして、まわりの人たちは、「今の自分でいいんだよ」という声かけをしたり、明るくニコニコと普通に接していればいいと思います。
時間はかかるかもしれませんが、ご本人がそのことに気づくことが一番なので、それを待つということも大切な関わり方だと思います。
私のまわりにも、自己肯定感が低い人がたくさんいます。
よくみんなが言っているのは、「あなたはあなたである」、「その状況にいてもいいよね」、「自分が自分でいれたり、やれていることを大切にしようね」等とまわりに人たちに言ってほしいそうです。
そしてどんな状況であれ、病気や障害があるからではなく、「私たちの今の状況を理解して、その人がその人らしくいられること」を応援してほしいとも言っていました。
まわりの人たちは、当事者の今を受け入れて、本当の姿を具体的に本人に伝えていくことが大切だと思います。
きっと自己肯定感が低くなっている人は、ほめてほしいとかなぐさめてほしいとかではなく、今ここにいる自分の姿を受けとめてほしいということなのかもしれません。