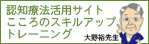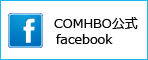特集3
スタートラインに立たせてくれたもの(223号)
○「こころの元気+」2025年9月号より
○申込について ○申込はこちら
○223号へ戻る
筆者:リマ(千葉県)
※筆者のX(旧Twitter)のアカウントは https://x.com/rima_etc8?s=21
▼大学進学をめざして
私は高校2年生のときに、うつ病とADHDと診断されました。
気分の波がはげしく、集中力も続かない中で勉強するのはとても大変でした。
それでも大学進学をめざし、日々できることを少しずつ積み重ねていました。
▼受験での配慮
受験では、センター試験と大学の個別試験の両方で「合理的配慮」を利用し、別室で受験をさせてもらいました。
当時は体調もあまりよくなく、大勢の中で試験を受けるのは本当にむずかしい状態でした。
静かな環境で、周囲を気にせずに試験に集中できたことは大きな助けになり、それまで勉強してきた成果をしっかり発揮することができました。
その結果、第一志望の大学に合格できたのです。
▼入学前の配慮
入学前から、大学のカウンセラーの方と面談の機会をいただけたのもありがたかったことの一つです。
「この先、どうやって大学生活をおくっていけばいいのだろう」という不安を、まだ何も始まっていない段階から受け止めてもらえたことが、心の支えになりました。
▼大学での生活
大学生活が始まってからも、体調の波は続きました。
調子のよい日ばかりではなく、授業に出られなかったり、試験に行けなかったりすることもありました。
特に試験期間中は、必ずしもベストな体調とは限らないので、レポートの提出期限を延ばしてもらえる配慮は本当に助かりました。
「ちゃんと元気なときに取り組めばいい」と思えるだけで、気持ちに余裕が生まれました。
また、コロナ禍でリモート授業が広がったことで、通学がむずかしい私にとっては大きな支えになりました。
コロナ禍が落ち着いた後も、リモート受講の選択肢を残してくれた先生が多く、自分の体調に合わせて学び続けることができました。
▼心に残る言葉
配慮を受けていく中で、ある先生がかけてくれた
「無理しないで、できる限りで大丈夫ですよ」という言葉が今も心に残っています。
配慮を受けながらでも、
「自分はこの場所で学んでいいんだ」と思えるようになりました。
▼相談してもいい
もちろん、自分でもできる工夫はたくさんしました。
時間の使い方やタスク(やるべきこと)の分解、優先順位のつけ方など。
でも、何よりもありがたかったのは「相談してもいい」と思える環境があったことです。
支援員さんや先生に困っていることを伝え、それに対して一緒に考えてくれる人がいることが、安心して学ぶ土台になっていました。
▼配慮を受けることは自分を知ること
配慮を受けることは、特別扱いではなく、みんなと同じスタートラインに立つための工夫だと感じています。
そして配慮を受ける過程では、「自分にはどんなサポートが必要なのか?」と自分に問いかける場面が何度もありました。
その経験は、就職活動の自己分析でもとても役立ちました。
自分を知ることは、人生のどんな場面でも大切なのだと気づけたのです。
▼踏み出すきっかけに
合理的配慮という言葉は少しかたく聞こえるかもしれませんが、私にとっては「ハンデをかかえる人が、がんばるための工夫」だと思います。
自分ひとりの力だけでは乗り越えられない壁も、支えがあれば越えられることがある。
そう実感できたからこそ、今の私があります。
この制度や姿勢が、もっと多くの人にとって、安心して一歩を踏み出すきっかけになればいいなと思っています。