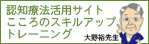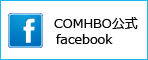特集1
合理的配慮とは何か? 基本のキ(223号)
○「こころの元気+」2025年9月号より
○申込について ○申込はこちら
○223号へ戻る
筆者:山口創生
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
地域精神保健・法制度研究部
▼合理的配慮
「合理的配慮」という言葉を耳にしたことのある方は多いと思います。
障害者権利条約の定義をもとに合理的配慮を簡単に説明すると、
「障害当事者の人権や自由の確保のために、個々の状況に応じて周囲や環境を変更・調整したりするが、過度の負担を課さないこと」となります(※1)。
さらに簡単にいうと、
私達のまわりには、障害のない人には何でもなくても、障害のある人にとっては「壁(バリア)」に感じることがあり、その「壁」のせいで活動がむずかしくなってしまうことがあります。
合理的配慮は、その「壁」をできる範囲で取り除こうという考え方です。
たとえば企業で働くとき、障害当事者の中には、一度にたくさんのことを言われたり、あいまいな説明をされたりすると困る人もいます。
そんなとき企業ができる合理的配慮として
「これを、この順番でやってね」と書いたメモを渡したり、
パソコンやスマホで、いつでも仕事内容を確認できるようにしたりすることがあげられます(※2)。
▼法律的な決まり
最近、合理的配慮がさまざま場面で使われるのは、法律的なきまりがあるからです。
具体的には2024年4月の障害者差別解消法の改正があげられます。
以前は合理的配慮の提供義務は行政機関のみでしたが、改正により一般企業でも義務化され、これにより多くの人が合理的配慮を意識するようになりました。
合理的配慮には、
視覚障害当事者への音声読み上げソフトの提供、
聴覚障害当事者への手話通訳者の配置、
精神障害当事者への働く時間・日数の調整や静かな部屋の確保
などの例もあります。
▼課題
合理的配慮が進むのは地域社会のためによいことですが、課題もあります。
1:企業の大きさや理解の問題
特に小さな企業では人手が足りず、障害当事者から「こうしてほしい」と言われても、すぐに対応できないことがあります。
また企業規模に限らず、合理的配慮についてよく知らない職員もいるでしょう。
このような場合、当事者が望む形での合理的配慮がむずかしいことがあります。
2:権利と立場の問題
法律で「合理的配慮をしなければならない」と決まったということは、障害当事者にとっては「お願い」ではなく「あたりまえの権利」です。
しかし実際には、合理的配慮を「する側」(行政機関・一般企業)と「される側」(当事者)という関係ができてしまいがちで、そんな状況では、当事者が合理的配慮を言い出しにくいこともあるでしょう。
合理的配慮と訳された「reasonable accommodation」は、「障害者に思いやりを持って接する」といった意味よりも 「環境調整を行う」という意味の言葉です(※3)。
「する側」「される側」に分かれるのではなく、互いに話し合い、どうすれば「壁」を取り除けるか一緒に見つけていく作業ともいえます。
精神障害の場合、困りごとが個人で大きく異なるため、このようなコミュニケーションは特に大切でしょう(※4)。
▼ちょうどいい配慮から
問題解決のためには「ちょうどいい配慮」から始めるのがよいかもしれません。
どんなきれいごとを言っても、障害者の権利を考えてこなかった人には、合理的配慮は急に降ってきた話です。
いきなりむずかしいことを考えず、まずは自分のまわりの人のことを、少し気にかけてみる、少し大切に思ってみる、少し話しかけてみることから始めてみます。
もし「他の人に親切にしても自分には関係ないな」と感じる人がいたら、「人に親切にすると実は自分も幸せな気持ちになれるんだよ!」(※5)と伝えてみるのもいいかもしれません。
▼障害当事者だけでなく
「ちょうどいい配慮」の対象には、子育てや介護で忙しい人など、いろんな事情の人がいます。
自分と違う事情の人に気を配ったり話したりすることで、
「この人はこんなことに困っているんだ。じゃあ、こうしてみようかな」
と気づくきっかけになれば、それが「合理的配慮」につながる糸口になるでしょう。
合理的配慮はルールとして少しずつ広がっています。
これからは、障害当事者が「こうしてください」とお願いするだけでなく、皆がふだんの生活の中で、自然に「ちょうどいい配慮」を互いに見つけられるような方法を考えていくことが大切と思います。
参 照
※1:外務省:障害者権利条約. 2024.
※2:内閣府:合理的配慮等具体例データ集:精神障害. 2025.
URL: https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index_seishin.html
※3:藤井千代:障害者総合支援法と障害者差別解消法. 臨床精神医学, 46(4);397-402, 2017.
※4:鎌田直樹:企業における合理的配慮の実際と課題:産業医の立場から. 産業精神保健, 31(2);89-93, 2023.
※5:Lim MH, Hennessey A, Qualter P, et al: The KIND Challenge community intervention to reduce loneliness and social isolation, improve mental health, and neighbourhood relationships: an international randomized controlled trial. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 60(4);931-942, 2025.