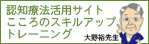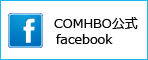特集3
薬をのみたくない気持ちについて聞きたい(222号)
○「こころの元気+」2025年8月号より
○申込について ○申込はこちら
○222号へ戻る
回答者:ジョーダン・藤原由紀・高橋哲
生活支援センター夢の実
初めに回答者それぞれの薬とのつきあい方の体験談
次に以下の4つの質問に答えていただきました。
▼質問
Q5 子どもが薬をのまない。どうしたら?
Q6 患者だと認める気がしてのみたくない。どうしたら?
Q7 薬がトラウマに。どう向き合えば?
Q8 やめたほうがいいと友人に言われた。どうしたら?
▼薬とのつきあい方の体験談
●10年かかった
筆者:ジョーダン
私は自分に合う薬に出会うまで10年くらいかかりました。
抑うつ等でたくさんのんでいて、とてもだるかったです。
10年前ピアサポート講座に出会い、自己肯定感が持てるようになった頃から薬が減っていきました。
またさまざまな薬を試していくうちに合う薬がわかってきて、数年前から体も楽になりました。
突然襲ってくる不安への耐性は弱くなっているような気がしますが、眠れるようになり、ふだんの不安は減っています。
●薬とのつきあい方
筆者:藤原由紀
初めてお薬をのんだのは15歳で「処方されているからのんでいる」でした。
副作用か病状かわかりませんが、
朝起きられない・身体が重い・やる気が出ない・がんばれないという症状に悩まされ、それを先生に訴えると薬が増えるという状況が8年ほど続きました。
副作用をおさえるために薬が増え、ひどいときは字も書けませんでした。
「のみたくないけど、のむしかない」という気持ちでした。
現在はPTSDに効くという漢方と睡眠薬とパニック発作のときにのむ頓服を処方されています。
効かないときもありますが、昔よりお薬とのつきあい方はうまくなったと思います。
今は何がつらくて、この薬はなぜのむのか、効かないときは疲れすぎたときかな?
などと考えられるようになりました。
●1つの手段
筆者:高橋哲
発病当初は病気のこともわからず、どのような薬をのんでいるのかもわかりませんでした。
病状の苦しさ、生きづらさから人生をあきらめ、よくなりたいという気持ちもありませんでした。
その後、居場所や仲間ができたことや合う薬と出会ったことで病状は安定してきました。
のまなくても平気かと思って怠薬して調子を崩したこともありましたが、今は自分の生活のベースを作る1つの手段という気持ちで薬をのんでいます。
また、調子を崩したときは調整もしてもらっています。
▼質問と回答
Q5
家族です。子どもが薬をのんでくれません。どうしたらよいですか?
A
ご本人はどうして薬をのみたくないのでしょうか?
薬の必要性を感じているのでしょうか?
このことをどのように感じているかが大切だと思います。
ご本人の薬や病気への想いに寄り添い、話を聞けるとよいと思います。
ご家族の理解や一緒にリカバリーしていこうという姿勢は本人にとって大変心強いと思います。
また、実際に薬をのんでいる体験談を聞くことも大切なことだと思います。
Q6
薬をのむと、自分が精神科の患者だと認める気がしてのみたくないのですが、どうしたらよいですか?
A
病気を受け入れることはとても大変なことです。
認めたくない気持ちは当然のことだと思います。
まずは認めたくない気持ちや苦しさ、生きづらさなどを聞いてもらい、寄り添って理解しようとしてくれる人を作ってみてはどうでしょう。
Q7
昔、病院で看護師に無理矢理薬をのまされ続けてトラウマに。
薬とどう向き合えばよいですか?
A
無理やりのまされるのは、怖くて傷つく非常に苦しい体験だったかと思います。
薬から当時のことを連想し、嫌になることもあるかもしれません。
きっと怖い体験をしたことから、薬も怖くなってしまったのですね。
薬と体験を切り分けていけると、少し楽になるのではないでしょうか。
薬の知識や必要性等を知ることで「薬はあくまで薬でしかない」というように、気持ちの変化が生じる助けになるのではないかと思いました。
Q8
友人が「精神科の薬は依存性があって怖いから、のむのはやめたほうがいい」と言います。
やめたほうがいいですか?
A
あくまでもご友人の意見、考えではありますが、薬は体にさまざまな影響があるかと思います。
「のみ続けていて大丈夫かな」と心配になることもありますよね。
とはいえ薬には、あなたを助けてくれる部分も大きく、必要性もあるでしょう。
この葛藤の中で、妥協して薬をのまなければならない状況を経験している仲間は多くいます。
薬についての困りごとなどを共有し合えると、気持ちが楽になり、どうして薬をのんでいるのか、必要なのかということに向き合えるかと思います。
○「こころの元気+」2025年8月号より
○申込について ○申込はこちら
○222号へ戻る