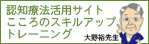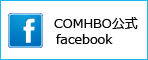ちょっと知りたい! ※連載について→コチラ
第122回
セカンドオピニオン(219号)
○「こころの元気+」2025年5月号より
○申込について ○申込はこちら
○219号へ戻る
筆者:白石弘巳
埼玉県済生会 なでしこメンタルクリニック
▼セカンドオピニオンとは?
医療を受けるとき、主治医は患者に対し、その同意を得るために診断や治療の方針について説明します。
ここで「主治医がする説明」がファーストオピニオンです。
そして「主治医以外の専門家から診断や治療に関する意見を聞くこと」がセカンドオピニオンになります。
▼セカンドオピニオンを求めるのは
セカンドオピニオンを求めるのは、「主治医の説明だけでは治療を受ける決断ができない」と感じるときです。
がんと診断されたある男性は、「手術と放射線療法のどちらを選んだらいいかについて、他の医師のセカンドオピニオンを得たことで不安が軽くなり、主治医の勧める治療法を選ぶ気持ちが固まった」と話されています。
私の経験では、精神科に入院中の患者さんについて、主治医から「電気けいれん療法を行う必要がある」と言われたご両親が、その効果や安全性について相談しに来られたことがありました。
このように、セカンドオピニオンには「意思決定のための補助手段」という意義があります。
しかしそれ以外の目的、たとえば、
「転医のための相談」
「医療訴訟に向けた助言」
などはセカンドオピニオンの対象外になります。
▼検査や結果
セカンドオピニオンは、新たに検査することなく、主治医からの診療情報提供書や、主治医のもとで実施された検査結果資料にもとづいて行われます。
また、相談の結果は主治医に報告されます。
従って、主治医に内緒で行うものではありません。
▼受けるときには
セカンドオピニオンは、「セカンドオピニオン外来」がある医療機関などで受けられます。
主治医から紹介してもらうこともできます。
▼支払いについて
主治医が提供する診療情報提供書は医療保険でまかなえますが、セカンドオピニオン先では、相談料という形でその病院が定めた金額を支払います。
その金額については利用の前に確認しておくとよいでしょう。
なお、セカンドオピニオンの対象とならない治療に関する相談ごとはいろいろあります。
小さなことでも気軽に安心して相談できる人が身近にいることが望まれます。
○「こころの元気+」2025年5月号より
○申込について ○申込はこちら
○219号へ戻る