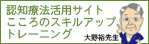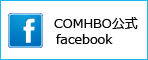Q 私の夫は三二歳の公務員で、躁うつ病です。病院には、約一年前に何回か行ったきりで、「自分は病気ではないから」と言って行かなくなってしまいました。職場にも行ったり行かなかったりです。電話の様子からして、職場も対応には困っているようです。職場を休んでいるときは、ボーっとして何もしません。「俺は役に立たない人間だから、役所をやめる」とか、「遺書を書くからメモをしてくれないか」と何度も言われました。躁状態のときには、ビデオで同じ映画を何回も繰り返し観たり、自分の好きな写真家の写真集を観ながらうなったりしています。そうしたときは困らないのですが、電話魔になり、友人や私の母親と二時間以上は電話でしゃべりっぱなしです。必要のない自動車を購入してしまうし、私の知らない間に生命保険にも入ったりして、お金のやりくりにはいつも困ってしまいます。
お伺いしたいのは、躁うつ病の人は、何を考えているのか、ということです。私は夫がどんな気持ちなのか、どんな思いでいるのかを知りたいのです。そして、治療を拒否していますが、やはり治療は必要なのでしょうか。皆さまのご意見をお聞かせいただければと存じます。よろしくお願いいたします。
A 外来とカウンセリング/寺澤真さん(神奈川県)
私は、四七歳で躁うつ病の当事者です。最近二度目の躁転(急に躁状態になること)を経験し、母をとてもつらい目にあわせてしまいました。それを反省し、これからの人生を見直す意味でも、私がどんな気持ちになったかをカミングアウト(病状表明)したいと思います。私の場合、躁状態になると頭の回転がとても速くなり、インスピレーションにあふれ、行動的になります。それがともすると対人関係において他罰的になり、相手に対して自分の主張ばかり押しつけるようになります。同時に、買い物も歯止めがきかなくなり、多額の買い物をしたりしてしまいます。
しかし、本人はいたって爽快な気分で、購入後の支払い計画などまったく考えていないので注意が必要です。私は、一度目の躁転で妻と離婚することになりました。そして、今回の躁転で母の信用を失うところでした。しかし、正気に戻った今では、当時のことを反省し、母や元妻の助言により、健康を回復しつつあります。
躁うつ病には、治療は欠かせないと考えています。私の場合、精神科の外来とカウンセラー、そして会社のカウンセラーに隔週一回の間隔で受診し、自分の状況をチェックしてもらっています。
もしあなたが配偶者を愛しているのなら、つらいときには離れて暮らすなど自分の精神状態にも充分配慮し、地道にご本人が自分の精神疾患について理解を深めていくことが大切だと思います。
A 重症になる前に受診を/益子雅苗さん(精神科医・内科医)
躁うつ病とは、簡単にいうと「エネルギーが低下して、気分の低下が続く」うつ状態と、その反対に「エネルギーに満ちあふれ、気分の高揚が続く」躁状態という「気分の極端な波」が現れる病気です。昔は「循環病」と言われていたように、一生のうちに気分の変化が何回か訪れる場合が多く、気分の波がないときはいたって普通の状態であることが特徴です。家族など大切な人を亡くしたり失恋したりした後は、気分が落ち込み(抑うつ気分)、やる気が出ず(意欲の低下)、まわりに興味が持てない(興味の喪失)といったうつ状態になります。また宝くじが大当たりした後には気分が高揚して気前がよくなる、といった躁状態になるなど、気分の波はどんな人でも多かれ少なかれあります。
病気でない場合は、治療をしなくても元に戻ることが多いのですが、躁うつ病ではうつ状態や躁状態の程度や期間が「病気のために」「極端に」なっているため、気分の波がないときには決してやらないだろうといった行動を繰り返し起こすことになります。うつ状態における行動の代表例が、「自分は取るに足らないものだと悲観して自殺してしまうこと」であることが最近はよく知られるようになっています。逆に躁状態になると、愉快で陽気な気分からほとんど制御できない興奮に至るまで、さまざまな程度の爽快な気分が少なくとも数日間以上続き、「寝なくても大丈夫、寝るのも惜しい」とあまり睡眠をとらなくなり(睡眠欲求の減少)、注意力や集中力を保持できないために落ち着きがなく、頭の中ではいくつもの考えがまとまりなくどんどん浮かんでくる(観念奔逸)ため、多弁で話題をコロコロと変えながら話し続け(談話心迫)ます。このようなときは気が大きくなっていて(誇大的)、自分にはすごい能力があって何でもできると思い込んでいるために(自尊心の肥大)、実現不可能な途方もない計画に熱中したり、浪費したり、好色になったりします。
とても活発で社交的となりますが、まわりの人の能力がないように思えて見下すために傲慢な態度をとる、イライラして怒りっぽく、ときに疑い深くなり攻撃的になる、などによりトラブルを起こすこともみられます。このように重度となると、自己制御はできなくなり、日常生活や仕事・社会的活動性に支障をきたすようになりますが、症状改善後には「われに返り」、悩み苦しむことになるものの、取り返しのつかないことになっていることも少なくありません。そのようなことを避けるためには、やはり治療が必要です。気分障害は、薬物治療やその他の治療によって改善が見込める病気なのですが、治療へつなげるためには、症状があるときと症状が消えているときの二つの工夫が必要です。
症状があるときは病気によって思考力や判断力が低下し、病気であることが認識できなくなるために、この方のように医療機関の受診をしたがらなくなりますから、重症化する前に受診をすすめることが重要となります。気分の変化だけではなく、心身ともに多くの症状が起こるため、身体の病気を治療する目的で受診をすすめてみるのもよいでしょう。治療は休養と気分安定薬を主体とした薬物療法を行い、これらによって睡眠や誇大的な気持ちなどの症状は改善します。それでも重症化してしまう場合は入院による治療もためらってはなりません。
一方、症状が落ち着いてきたら、「治った」と思って治療をやめるのではなく、気分障害という病気と治療について勉強し、さまざまな方法(認知行動療法やストレスマネジメント、元気回復プランの作成など)を用いて、次回に症状が出現したときに、早めに対処するコツを学んでおくことが重要になります。周囲の人も、症状に気づいたら様子を見るのではなく、早めに「いつもと違う」旨を本人に伝え、受診をすすめることが重要です。