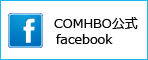「こころの元気+」2008年5月号より
単剤・低用量のススメ「ふつう」の薬物療法とは
おおぞらクリニック/八木 剛平
はじめに
統合失調症の治療にかかわって、四五年になります。薬がとくに必要で、有用とされる初発の急性期について、私の薬物療法の経験をお話しします。多種・大量の抗精神病薬を処方する同業者への批判としてお読みください。
なお薬の量は、すべてハロペリドール換算一日平均のmg数です(クロールプロマジンに換算する場合は、数値を五〇倍してください)。
私の処方歴(一九六五―九九年)
民間病院の入院治療…民間病院の常勤医だった一九六五―七八年に、発病後初めて入院された五七人への処方です。入院時に、隔離・拘束された人が約三分の一、注射を必要とした人が約三分の二いました。
抗精神病薬は、前半がクロールプロマジンかレボメプロマジン、後半は(その後に発売された)ハロペリドールが中心です。開始時に二種併用は六人だけで(単剤率は89%)、用量は4・0mg、抗パーキンソン薬の併用率は14%でした。その後の病状に対応して、最大用量は一時的に6・6mg、抗パーキンソン薬の併用率は(84%に錐体外路系の副作用が出たため)70%に達しましたが、回復した時点(平均九・九週後)の用量は3・0mgでした。
この時代の入院治療成績は、帰郷などの社会的理由による退院六人をのぞくと、回復退院が四五人(88%)、未治退院五人、死亡一人です。よくなった人は、徐々に減量・単剤化し、退院時の単剤率は85%、抗パーキンソン薬の併用率は22%、用量は2・4mgで維持療法に移行しました。
大学病院の外来治療…一九八六―九七年に大学病院の外来を、発病して初めて訪れた四〇人への処方です。応急処置を必要とした人はいません。前半は、入院治療の経験からおもにハロペリドールを使っていましたが、初めから抗パーキンソン薬を併用していても副作用が出るので、後半は当時うつ病の治療に処方していたスルピリド(非定型抗精神病薬)を使いました。
開始時は、すべて単剤で、用量は3・7mg、抗パーキンソン薬の併用率は15%でした。その後、最大用量は一時的に8・0mgになりましたが、回復時の用量は3・5mgです。平均五・八週後に三五人(88%)が回復し、未治は五人(二人は入院)でした。回復者の一年半後の維持療法は、単剤率83%、用量は2・6mg、抗パーキンソン薬の併用率は4・4%です。
結果のまとめ…最初の急性期は、精神病院でも大学病院でも、症状のはげしさと回復のスピードに違いはあるものの、また時代によって抗精神病薬の種類(クロールプロマジン、ハロペリドール、スルピリド)に違いはあるものの、原則として単剤療法で最終的には受診者の九割近くが回復されました。
そして急性期から回復した時点の抗精神病薬の用量は、3・0―3・5mg、再発予防のための維持療法は、単剤率83―85%、用量は2・4―2・6mgで、治療量・維持量をあわせて2―4mgの範囲でした。
科学的な根拠はあるのか
まず多種併用が、単剤にまさるという科学的な根拠は、約半世紀の研究でも出ていません。
次に用量ですが、一九六〇年代前後にはクロールプロマジン、一九七〇年代にはハロペリドールを使って、通常量の一〇―一〇〇倍に及ぶ大量療法が(ときには点滴静注で)試みられましたが、その後の研究で急性期にも慢性期にもほとんど役に立たないことが立証されました。
再発予防のための維持量も、それまでの通常量の五分の一ですむこともわかりました。
また一九八〇年代には、有効量はクロールプロマジン換算100―1000mg、ハロペリドールは5―15mgとされていましたが、一九九〇年代の研究で、急性期の最少有効量は平均3・4mgと報告されました。
その後の神経画像研究では、最適なドーパミン受容体の占拠率は60―80%で、これはハロペリドール2―5mgに相当するとのことです。私が使ってきた抗精神病薬の量は、ちょうどこの範囲におさまっていますから、試行錯誤でやってきた自分の薬物療法に科学的根拠が与えられたと考えています。
「ふつうの薬物療法」がなぜ「単剤・少量」になったのか
私が精神科医になった一九六〇年代の薬物療法は単剤が常識で、当時の教科書にはクロールプロマジンは「ふつう100―200mg」と書いてあります(添付文書の用量は50―450mg)。
また大学の精神薬理研究室のボスから、欧米には「多剤併用は医者の恥」とみる伝統があるという話を聞きました。その後発売されたハロペリドールは、当時0・75mgの錠剤だけで、これを一日三錠から六錠使うのが普通でした(添付文書の用量は3―6mg)。だから私がやってきたのは、昔からの「ふつうの薬物療法」なのです。
一九七三―七四年に処方の実態調査で、同じ病院や他のいくつもの病院の医師の処方と比較する機会があり、自分では「ふつう」だと思っていた処方が、他の医師に比べると併用率が低く、量も少ないことを知りました。しかし薬の種類や量をもっと増やしても治療成績がそれ以上あがると思えなかったので、その後も「ふつうの薬物療法」を続けているうちに、他の医師の処方がどんどん多種・大量化して、本来は「ふつう」の処方が「単剤・少量」ということになったのです。
一種類で長所が出るとされる新薬の時代になっても、二種類以上の新薬の併用や旧薬との併用が多いのは驚きです。
なお多種併用、それ自体は必ずしも非難されるべきこととは思いません。名医といわれる人の処方には多種併用が多いようです。しかしその場合は、「多種・微量」処方であって、けっして大量処方になることはありません。もちろん私に、そんな名人芸はできませんが。
なぜ多種・大量になるのか――病気への敵意と戦意?
実をいうと、統合失調症の処方がなぜ多種・大量化するのか、私にはいまだによくわからないのです。もちろん医師の悪意から出たことではなく、むしろ善意と熱意の産物でしょう。また日本各地の国立療養所でも、多種・大量処方が蔓延していることからみて、ひところいわれたように、民間病院のもうけ主義が原因でないことも明らかです。
どうも病気の見方、治療の考え方に問題がありそうです。代表的なのは幻覚・妄想・ドーパミン悪玉観です。薬物療法とは、脳内の神経伝達を遮断して、症状を取り除くことだという思い込みがあって、症状がとれるまで多種・大量の薬を脳に注ぎこもうとするのではないでしょうか。
多種・大量の処方例をみると、当事者は病気対薬の戦場になってしまっているようです。当事者に対して悪意でなくても、病気(症状)に対しては、処方医が敵意と戦意をもって立ち向かっているのではないでしょうか。
多種・大量処方から脱却するために・・・リジリエンスに注目を
「病気の症状は、すべていのちがよくない状態になっていることを教える働きと、回復しようとする自然治癒力の働きをどこかに含んでいる」と神田橋條治さんはいっています(風邪をひいたときの発熱をはじめとする症状がよい例です)。またドーパミン神経はストレス緩和システムの一つで、本来は病気を防いだり、回復を助けたりしているはずなのです(風邪をひいたときに働く免疫系のようなものです)。
昔から「病気をみて病人をみず」という批判の言葉があります。今はこれに加えて、「症状を知って、回復力を知らず」という批判も必要になりました。「自然治癒力」は、現代医学でほとんど死語となり、いわゆる伝統医学のなかで生き続けてきました。しかし最近「自然治癒力の現代版」ともいうべき「リジリエンス」という言葉が脚光を浴びています。
リジリエンスとは、病気に対する抵抗力(抗病力)のことです。病気の原因の発見・解明だけでなく、健康なときには病気を防ぎ、病気になったら悪化を防ぎつつ回復を助ける心身の働きを医学的に解明しようということになったのです。
これまでは、おもに心的外傷後ストレス障害やうつ病でしたが、いずれは統合失調症の薬物療法も、脳のなかの悪いところをたたいて症状をとるのではなく、当事者のリジリエンスを引き出し、強化する治療であることがはっきりするでしょう。
多種・大量処方から脱却して「ふつう」の処方にもどるには、まず医師、それに当事者とご家族が、病気の見方、治療の考え方をこのように変えていくほかないと思います。